5月5日は、「こどもの日」ですね。
我が家も男の子がいるので、毎年こどもの日には小さな鯉のぼりを出して飾っています。

男の子がいるご家庭は気になる内容ですよね。
そんな中で、気になったのが鯉のぼりを飾る時期についてです。
こどもの日は「端午の節句」といい、男の子の誕生と成長を祝う日です。
今回は、鯉のぼりを飾る時期や片付ける時期、何歳まで飾るのかについて紹介していきます。
鯉のぼりはいつから?
鯉のぼりを出す時期については、特に決まりはありません。
地域や家庭によっても異なり、飾る時期は「ひな祭りが終わってから」「春のお彼岸が過ぎてから」という人もいます。
一般的には、春分の日から4月下旬のよく晴れた日に用意することが多いようです。
また、吉日である大安の日に出すという家庭もありますよ。
3月3日のひな祭りの日にひな人形を飾っている家庭は、ひな人形を片付けてから鯉のぼりを飾る人が多いです。
ただ、ひな人形と鯉のぼりを同じ時期に飾っていけないという理由はありませんので、かぶっていても大丈夫ですので安心してください。
鯉のぼりはいつまで?
鯉のぼりを片付ける時期についても、出す時期同様に特に決まりはありません。
5月5日を過ぎたらすぐに片付ける方もいれば、地域によっては6月まで飾っている地域もあります。
一般的には、5月中旬に片付ける人が多いです。
片付ける日も特に決まってはいませんが、天気が良い日に片付けるのがおすすめですよ。
雨の日やじめじめした湿度が高い日に片づけをすると、虫がつきやすかったり、カビが生えてしまう可能性がありますので注意が必要です。
また、遅くなると梅雨になってしまいますので、遅くても梅雨がくるまでには片付けると長い間きれいに鯉のぼりを保管することが出来ますよ。
鯉のぼりは何歳までかかげるの?
鯉のぼりを飾る時期などはわかったけど何歳まで鯉のぼりは飾るべきなのか悩む方もおおいのではないでしょうか。
男の子が生まれて初めての端午の節句を「初節句」と呼びますが、このタイミングから鯉のぼりは掲げ始める人が多いです。
初節句で鯉のぼりを掲げるのは、「子供の出世を願う」親の気持ちが強く表現されています。
最初に掲げる時期は、今お伝えした通りですが何歳まで掲げるかについては意見が分かれます。
- 七五三を迎えた年齢
- 昔の元服の年齢である15歳
- 成人まで
何かの節目となる時期までを掲げるとしている人が多いようです。
特にこの時期までは掲げていなければいけないということはないので、家族でいつまで鯉のぼりを掲げるのか決めてみてはいかがでしょうか。
鯉のぼりを長持ちさせる方法はある?
鯉のぼりは、外に飾るもののため、雨で濡れてしまったり、風で傷ついてしまうこともありますよね。
では鯉のぼりを長持ちさせる方法はどんな方法があるのか紹介していきます。
雨や風の日は飾らないようにする
鯉のぼりを掲げる時期は、梅雨の前で雨が増え始める時期です。のため、そんな日は鯉のぼりを飾らないようにしましょう。
鯉のぼりの生地にもよりますが、雨にあたることで劣化してしまい、色が落ちてしまう可能性があります。ナイロン素材で出来ているようなものであれば、劣化はしにくいと言われていますが、酸性雨などで傷む可能性はありますので、どんな鯉のぼりでも長持ちさせたい場合は雨の日や風の日は飾らないようにするのがおすすめです。
汚れたら洗濯をする
鯉のぼりですが、最近は選択できるものが増えてきています。そのため、鯉のぼりが飾り終わったら洗濯をすると翌年もいい状態で使用することができますよ。
ただ、洗濯機やクリーニングに出すと、傷んでしまう可能性が高いため、手洗いをしていただくことをおすすめします!
浴槽やタライなどに30度から40度くらいのぬるま湯を用意して、中性洗剤で軽くもんだうえでつけおきします。つけおきは長くつけると色落ちの原因などになるので、30分から1時間くらいがよいかと思います。
そのあとは、優しく洗い流して日影干しをしていただくことで、綺麗な鯉のぼりの状態に戻すことができます。
乾燥させて保管をする
鯉のぼりは、濡れていたり、湿気が多かったりするとカビが生えてしまう可能性があります。
そのため、鯉のぼりをしまう時はしっかり乾燥をさせてからしまうように気をつけましょう。
鯉のぼりとは?
そもそも鯉のぼりとは、どんな由来があるかご存じでしょうか。
鯉のぼりとは、男の子の誕生と健やかな成長を願って、家の庭先に飾る「鯉の形を模して作ったのぼり」のことを言います。
鯉のぼりは5月5日のこどもの日、「端午の節句」に飾るものです。
5月5日は現在、こどもの日という祝日になっていますが、昔は「端午の節句」と呼ばれていました。こどもの日と端午の節句は、同じ日のことを表していますが、行事の意味や内容は少し異なります。
子どもの日とは?
こどもの日は、1948年に国民の祝日に関する法律によって定められた休日です。
子どもの人格を重んじて、子どもの幸福を願うととともに、母親に感謝をする日とされています。
端午の節句とは?
端午の節句とは、男の子の健やかな成長を祈願するための日です。
端午の節句は、もともとは中国の風習で、別名「菖蒲(しょうぶ)の節句」ともいわれています。
香りが強く邪気を払うとされている菖蒲(しょうぶ)や蓬(よもぎ)を門に挿し、菖蒲を浸したお酒を飲んで厄除けや健康祈願をしていました。
その後、「しょうぶ」が「勝負」や「尚武(武士を重んじる)」を連想させることから、武家で「男の子の元気な成長を祝う」という意味が加わりました。
鯉のぼりのタイプは?
鯉のぼりですが、昔は家の外に大きな鯉のぼりを飾ることが多かったですが、室内に置けるタイプの鯉のぼりもありますので、気軽に鯉のぼりの用意ができるようにもなっています。
室内用タイプ
マンションやアパート住まいの方は、外に鯉のぼりを出すことが難しいので、こちらの室内タイプを飾るのもおすすめです。
ベランダ用タイプ
マンションなどでもベランダに設置できるタイプのものです。
大きさがあるので、マンションやアパートに設置を検討している方は、大きさなどを事前にチェックしてくださいね。
庭用スタンドタイプ
一軒家で庭がある方はこちらがおすすめです。
少し大きく感じるかもしれませんが、本来の鯉のぼりという感じがしますよね。
鯉のぼりはいつからいつまで?飾る時期や年齢についても調査まとめ
ここまで鯉のぼりの出す時期や片付ける時期、どれくらいの年齢まで出しておくべきかについて紹介してきました。
特に決まった時期はなく、家庭によることが分かったと思いますので、家族で決めるといいですよね。
- 鯉のぼりを出す時期は決まっていませんが、春分の日から4月下旬のよく晴れた日に準備することが多い。
- 鯉のぼりは、一般的に5月中旬に片付ける人が多い。
- 何歳まで飾るかについては、家庭によりますが、節目となる時期まで掲げることが多い。
- 鯉のぼりを長持ちさせる方法としては、雨や風の日は出さない、汚れたら洗濯する、乾燥させてから保管するなどが秘訣としてあります。
- 鯉のぼりのタイプは色々あるため家庭にあったものを選びましょう。

子供たちにとっても特別な時間を過ごせるようぜひそれぞれの家庭にあったものを準備しましょう!

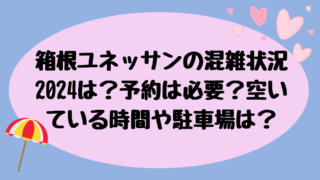
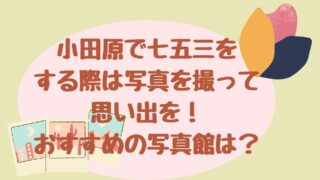
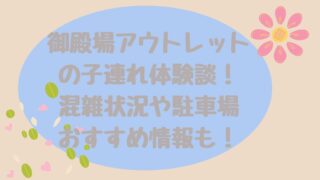
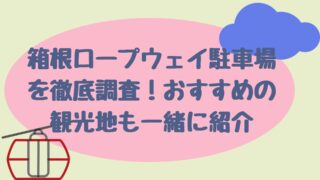
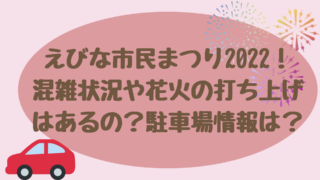
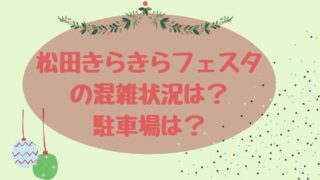
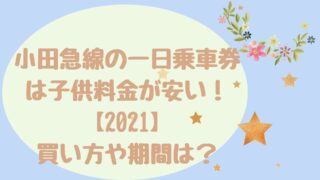
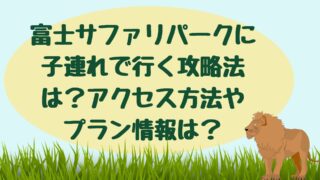
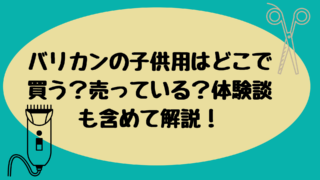
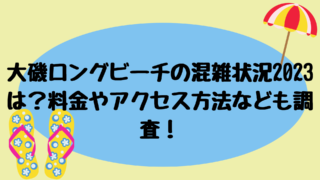
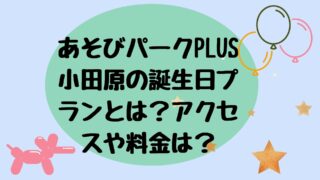
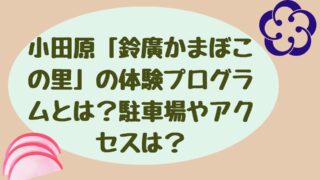
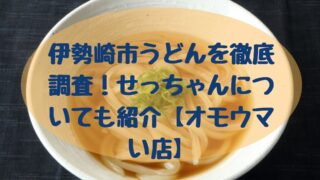
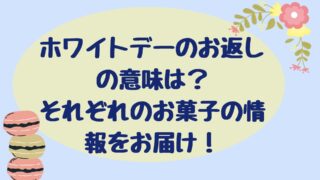
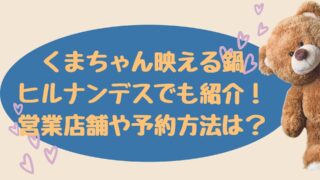
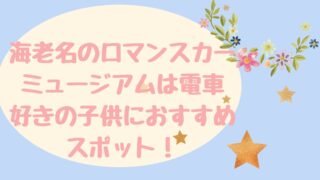
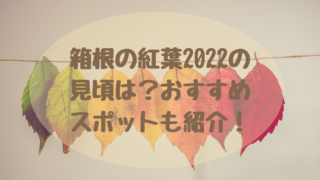
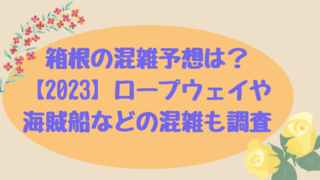
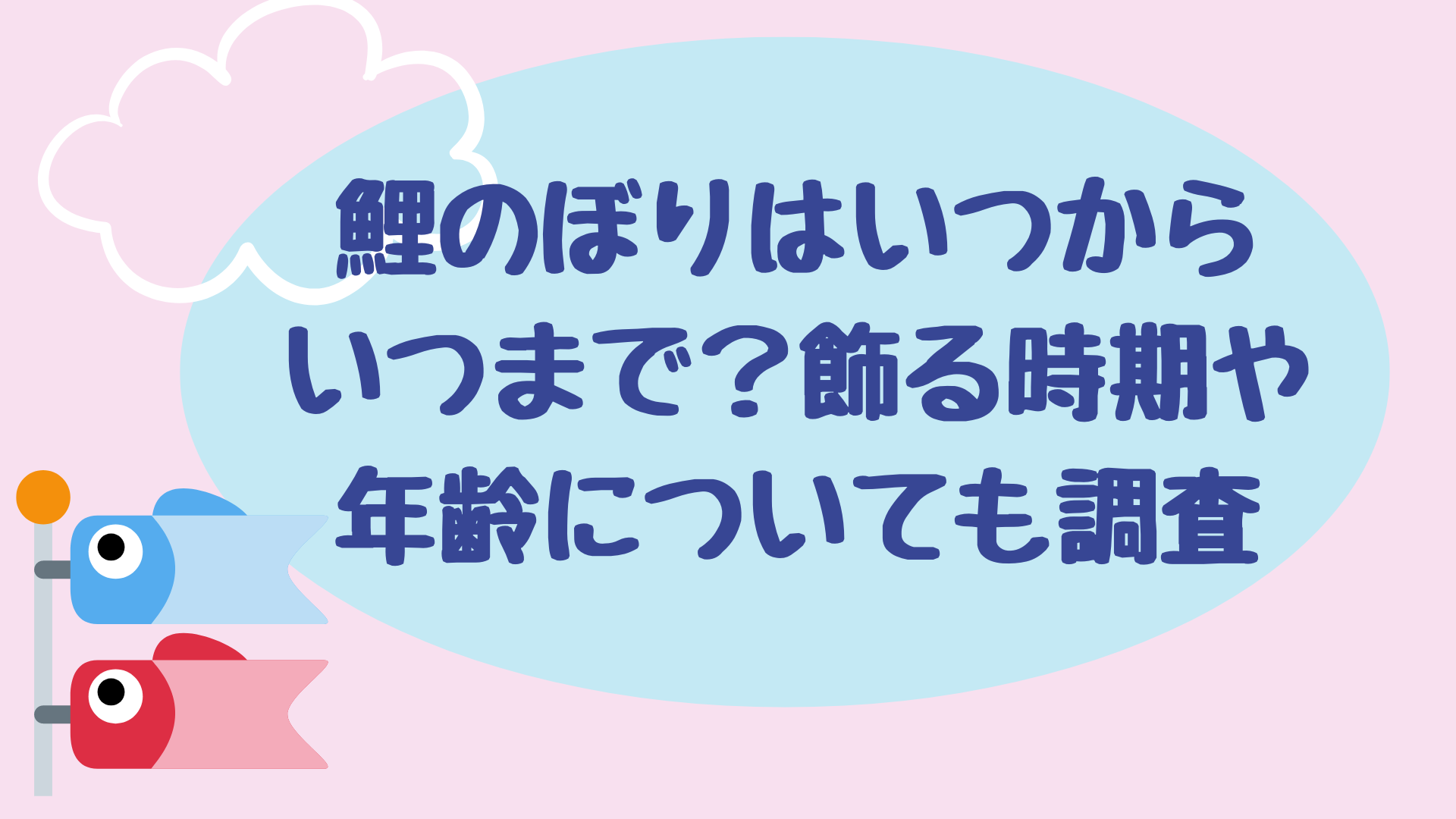









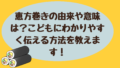
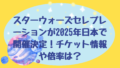
コメント